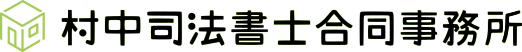遺言書の検認手続き|司法書士が流れ・費用を分かりやすく解説
 相続人
相続人遺言書を見つけたけれど、どうすればいいのだろう?



このまま開封しても良いのだろうか?
ご家族が亡くなられた後、このような不安を抱えてご相談に来られる方は少なくありません。
個人様がご自身で作成された遺言は、相続手続きを進める上で家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
その遺言書に封がされている場合、開封してはいけません。家庭裁判所での検認手続で開封することになります。
このページでは、熊本の司法書士が、複雑で分かりにくい遺言書の検認について、できるだけ分かりやすく解説します。ご安心してお読みください。
その遺言書、検認は必要?
全ての遺言書に検認が必要なわけではありません。以下の表で、お手元の遺言書に検認が必要かどうかをご確認ください。
| 検認の要否 | 遺言書の種類 | 特徴 |
| 〇必要 | 自筆証書遺言 | ご本人が手書きで作成し、自宅などで保管されていたもの。 |
| 〇必要 | 秘密証書遺言 | 内容は秘密で、存在だけを公証役場で証明してもらったもの。 |
| 不要 | 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成に関与したもの。 |
| 不要 | 法務局で保管した遺言書 | 自筆証書遺言を法務局の保管制度に預けていたもの。 |
遺言書の検認とは?


検認とは、「家庭裁判所による遺言書の現状確認」です。
相続人全員に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書がどのような状態で発見されたか(形状、日付、署名、訂正跡など)を裁判所が記録し、偽造や変造を防ぐために行います。
【重要】検認は遺言の有効性を判断するものではありません
検認はあくまで遺言書の「状態」を確認する手続きです。日付がないなど、法律上の要件を満たさない遺言は、検認を経ても無効となる場合があります。
検認手続きの流れ
検認は、おおむね以下の流れで進みます。申立ての準備から完了まで、通常1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。
STEP 1:必要書類の収集
申立てには、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本など指定された戸籍類を添付します。
▼
STEP 2:家庭裁判所への申立て
当事務所が代理で申立書を作成し、家庭裁判所へ提出します。
▼
STEP 3:検認日の調整・通知
裁判所と日程を調整します。その後、裁判所から相続人全員へ「検認日のお知らせ」が郵送されます。
▼
STEP 4:検認日の実施
申立人(相続人の代表者様)に、遺言書を持って家庭裁判所へお越しいただきます。
▼
STEP 5:検認済証明書の交付
手続き後、遺言書に「検認済証明書」が付けられ、各種の相続手続きに使用できるようになります。
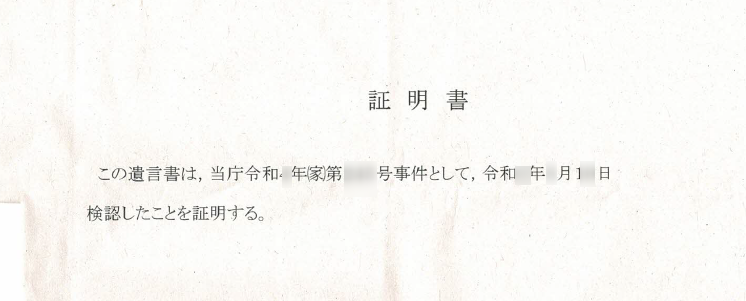
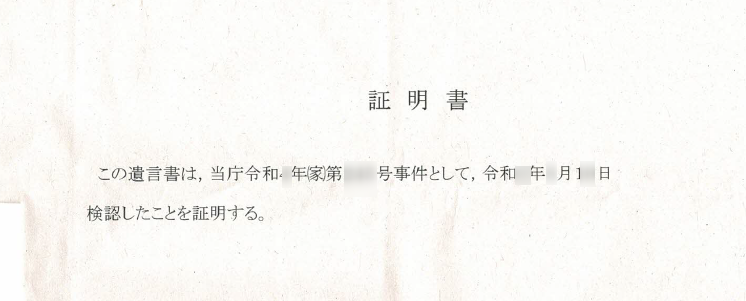
4. 司法書士に依頼するメリット
メリット①:時間と手間の削減
戸籍謄本の収集や申立書の作成を全て代行します。
お客様には、指定された日に一度だけ、家庭裁判所へお越しいただくだけで済みます。
メリット②:正確・円滑な手続き
専門家が正確な書類を作成することで、不備による手続きの遅れややり直しを防ぎます。
メリット③:相続手続きをまとめて任せられる
検認後の不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約まで、その後の煩雑な相続手続きも一貫してサポートいたします。
5. 検認申立ての費用について
当事務所にご依頼いただく場合、「司法書士報酬」と「実費」がかかります。
司法書士報酬
- 検認申立書作成サポート: 22,000円(税込)
- 戸籍等の取得代行: 1通あたり1,650円(税込)
実費
- 戸籍発行手数料、収入印紙・郵便切手代など通常、10,000円~15,000円程度です。
6. よくあるご質問
Q. 誤って遺言書を開封してしまいました。
A. 開封しても遺言が無効になるわけではありませんのでご安心ください。ただし、法律上は過料(罰金に類するもの)が科される可能性があります。
Q. 相続人全員が裁判所に行く必要はありますか?
A. 全員が行く必要はありません。申立人は遺言原本をお持ちいただき家庭裁判所へお越しいただきます。



遺言書のことでお困りでしたら、まずはお気軽にご相談ください。